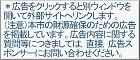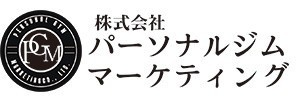【校長室から】あの時試されていたものは。
- 公開日
- 2026/01/21
- 更新日
- 2026/01/22
校長室から
共通テストの二日間を終えた。
会場である大学のキャンパスのその先に、朝陽がまっすぐに差し込んでいた。寒さの輪郭が少しだけゆるみ、人の表情も、どこかすっきりして見えた。
その前日――大学入学共通テストを目前にした「25期生激励会」のこと。
会場である講堂には、しんとした空気があった。ざわつきがない。椅子の軋む音さえ、遠慮がちに聞こえるような静けさだった。冬の室内に特有の、少し乾いた空気の中、3年生の生徒たちは、まっすぐに前を見ている。どの顔にも余計なものがない。静かな集中。目は冴えていた。
担任団の先生方が語り、学年主任が語り、進路指導主事が語った。どの言葉も飾り気はない。けれど温かい。そして熱い。立場は違っても、まっすぐに言葉が注がれる。抑制の効いたトーン。しかし心の芯を揺らすように語られる。「ここまで来たな」という確かな歩みが背景にある。そこに、ここまで積み重ねられた日々がにじんでいた。「激励会」は、高校3年間の締めくくりの段階にある25期生に対しての贈物。もちろん、共通テストだけを対象としたものではなく、受験や卒業に向かう生徒を励ます意味合いで行われる。
教員からの語りで印象的だったのは、自分自身が受験生だった頃の話が多かったことだ。試験会場へ向かう朝の空の色。前夜に眠れなければどうしていたか。緊張をほぐすためのルーティンは何だったか。実感を伴った過去が語られると、生きた経験として聴き手に届く。生徒たちは、その言葉をまっすぐに受け止めていた。静かに、深く。
そんな光景を見ながら、30数年前の自分を思い出す。センター試験。会場は京都大学農学部だった。冬のキャンパスは硬質で、空気が冷たく、建物の輪郭がくっきりしていた。地面から上がってくる冷えが靴底を通して伝わり、歩くたびに自分が「試される場所」へ向かっている感覚であったように記憶する。試験科目の合間にトイレに立った時のことだ。廊下の一角で、同じ学校らしき見知らぬ生徒同士が、大声で話していた。「あの問題がどうだった。」「この問題の正解はこれだ。」 私たち他校の生徒を意識するかのような大きな声で。
内心、「静かにしてくれ」と思った。集中を乱されたくない。まだ次の科目が残っている。余計な情報を入れたくない。けれど、その次の瞬間、自分の中で別の声が立ち上がった。「そんなことを気にしている、自分自身が小さいのだろう。」「他人は他人、自分は自分。」「他校の生徒の会話が何であろうと、それがどうした。」
そう考え直した記憶が、今でも妙にくっきり残っている。あのとき私は、「センター試験」に試されていたのではなく、「自分の心の持ち方」を試されていたのだと思う。目の前の喧騒に振り回されるか。自分の呼吸を取り戻せるか。この大地を、自分の脚で立ち、自らの足で踏みしめ、前に進んでいく…。受験とは、そういう局面の連続でもある。
今となっては、センター試験の点数など覚えていない。あの日の気温が何度だったかも知らない。昼食を何時に食べたかなど、覚えていようはずもない。数字や出来事は、いずれ忘れられていく。色褪せ、かたちを失っていく。けれど、経験は消えない。その時に何を考え、どのように振る舞い、行動したか。何に立ち向かい、何に挑戦したのか。それだけは、消えてはいかない。消えないからこそ、人生を支える。人は、挑戦した経験とともに生きていくのだと思う。
「激励会」で、担任団の先生方が語り、学年主任が語り、進路指導主事が語った。その後、送られた拍手は大きすぎず、しかし確かだった。会が終わり、講堂を後にする生徒たちの背中は、頼もしく見えた。
翌日から、共通テストの二日間が始まった。全国でおよそ50万人が、この日に向かって歩いてきた。
試験会場へ向かう足音。静かな緊張。背筋を伸ばしながら、少しだけ早足になる。きっと同じように、駅のプラットホームで、バス停で、電車の中で、それぞれの受験生が小さく息を整えていたのだろう。
共通テストを終えた25期生もまた、この二日間で「消えないもの」を手に入れた。努力を結果に結びつけるために学び、工夫し、積み重ねる。その営みの尊さは、言うまでもない。けれど同時に、結果がどうであれ、「立ち向かった」という事実だけは、一生、私たちを支えてくれる。もしも「立ち向かえなかった」自分がいたとしても、構わない。若者には「次」がある。「次の機会」に挑戦すればよい。
そして今、まさに「次」に向かっている。挑戦した自分は残る。その自分と一緒に、これから先を生きていく。
温かい冬の日差しの中で、ふと思う。数字が忘れられたあとにも、なお、残るものの方が、きっと大きい。
堀川高校生の冬の挑戦は、続いていく。
ここからのチャレンジを楽しんでいこう。
船越 康平