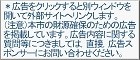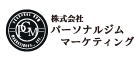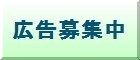学校日記
文部科学省「高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)」指定校(R6年度~R7年度)
-
北川 進先生(ノーベル化学賞受賞)が所属する京都大学iCeMS(アイセムス)を訪問しました!No.3
- 公開日
- 2026/01/16
- 更新日
- 2026/01/16
校長室より
さる12月25日(木)、本校の前身である塔南高校の卒業生で、ノーベル化学賞を受...
-
北川 進先生(ノーベル化学賞受賞)が所属する京都大学iCeMS(アイセムス)を訪問しました!No.2
- 公開日
- 2026/01/16
- 更新日
- 2026/01/16
校長室より
さる12月25日(木)、本校の前身である塔南高校の卒業生で、ノーベル化学賞を受...
-
北川 進先生(ノーベル化学賞受賞)が所属する京都大学iCeMS(アイセムス)を訪問しました!No.1
- 公開日
- 2026/01/16
- 更新日
- 2026/01/16
校長室より
さる12月25日(木)、本校の前身である塔南高校の卒業生で、ノーベル化学賞を受...
-
書道部が第5回全国高等学校書道パフォーマンスグランプリ決勝大会に出場しました
- 公開日
- 2026/01/16
- 更新日
- 2026/01/16
スクール・ライフ
1月11日(日)、「第5回全国高等学校...
-
南区まちづくりに関する意見聴取に協力しました
- 公開日
- 2026/01/08
- 更新日
- 2026/01/08
スクールライフ
本校において、京都市南区役所 地域力推進室の皆様をお迎えし、「南区まちづくり運...
-
-
-
府市合同「京都探究エキスポ」で開建生が躍動いたしました!No.3
- 公開日
- 2025/12/25
- 更新日
- 2025/12/25
スクールライフ
「京都探究エキスポ」は国際会館のアネックスホールとイベントホールの2つの会場で実...
-
府市合同「京都探究エキスポ」で開建生が躍動いたしました!No.2
- 公開日
- 2025/12/25
- 更新日
- 2025/12/25
スクールライフ
「京都探究エキスポ」は国際会館のアネックスホールとイベントホールの2つの会場で実...
-
吉祥院図書館「クリスマスお楽しみ会」に本校生徒がボランティア参加しました
- 公開日
- 2025/12/25
- 更新日
- 2025/12/25
スクールライフ
12月20日、吉祥院図書館で開催された「クリスマスお楽しみ会」に、本校の生徒がボ...
-
【1年生】八木かつら様へフィールドワークに行ってきました。
- 公開日
- 2025/12/25
- 更新日
- 2025/12/25
スクールライフ
1年生の希望者3名で、100年前から続く時代劇や演劇用かつらの老舗八木かつら様で...
-
【1年生】冬のキャリアウィーク3日目
- 公開日
- 2025/12/25
- 更新日
- 2025/12/25
スクールライフ
1年生冬のキャリアウィーク3日目は、キャリアガイダンスと佛教大学の原先生による講...
-
【1年生】冬のキャリアウィーク2日目
- 公開日
- 2025/12/25
- 更新日
- 2025/12/25
スクールライフ
1年生冬のキャリアウィーク2日目は、5名の講師の方々に起こしただきました。 講師...
-
【2年生】冬のキャリアウィークを実施いたしました!
- 公開日
- 2025/12/25
- 更新日
- 2025/12/25
スクールライフ
12月22日(月)から24日(水)まで、2年生全員を対象とした「冬のキャリアウ...
-
「京都探究エキスポ」で開建生が躍動いたしました!No.1
- 公開日
- 2025/12/24
- 更新日
- 2025/12/24
スクールライフ
12月20日(土)、国立京都国際会館で「京都探究エキスポ」が開催されました。京...
-
【1年生】冬のキャリアウィーク・龍谷大学における探究学習を実施していただきました!
- 公開日
- 2025/12/24
- 更新日
- 2025/12/24
スクールライフ
冬のキャリアウィーク1日目の本日は、龍谷大学において、大学での探究学習を実施し...
-
国際日本文化研究センターにて探究活動を行いました!
- 公開日
- 2025/12/22
- 更新日
- 2025/12/22
スクールライフ
日本文化に関する国際的・学際的総合研究拠点である「国際日本文化研究センター」(日...
-
【2年生】堀川高校短期留学プログラムを実施しました!
- 公開日
- 2025/12/17
- 更新日
- 2025/12/17
スクールライフ
12月15日(月)・16日(火)の2日間、開建高校の生徒8名が堀川高校での授業や...
-
本校の写真同好会メンバーが作品を出展いたしました!
- 公開日
- 2025/12/15
- 更新日
- 2025/12/15
スクールライフ
秋が深まる中、嵐山にある二尊山 西光院にて開かれた「ぼんちきよしと中高校生アー...
-
【吹奏楽部】本校部員も所属するThe Gryphonsが全国大会に出場しました!
- 公開日
- 2025/12/11
- 更新日
- 2025/12/11
スクールライフ
本校吹奏楽部現役部員の8割と3年生2名が所属する一般マーチングバンドThe G...